■登場した遺跡・場所
ギルフ・キビール(エジプト)
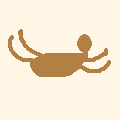 ★へっぽこ絵 ★へっぽこ絵
スイマーと呼ばれている絵です。
伸びた手足が気持ちよさそうです。
私は落下しているところかな…と思いました。
教育テレビ「ETV」で放送された、「なぜ人は絵を描くのか〜日比野克彦・サハラ1000キロの旅」を見ました。
NHK総合で放送された「ギルフ・ケビール」の放送を再編集して一本作ったものでした。
ただNHK総合では絵を描いていませんでしたが、こっちではスケッチしてました。
「世界ふしぎ発見」でカナエ女帝が見に行った岩絵と全く同じ切り口で、「どっちが先に真似たのか?」と思わずにはいられませんでしたが、自分がこんな奥地に行くことは無理そうなので、こうやって紹介してくれるのはありがたいことだと思いました。
ルポした日比野克彦さんがこだわっていた「なぜ人は描くのか?」という問いですが、絵描きがその答えを探すというのは矛盾しているように思いました。
特に現代に生きて、自由に描くことを許された日比野さんの場合、自分の胸に手を当てて考えれば答えは出るんじゃないですか?と、私は思うのです。
私がああいう岩絵を見て不思議に思うのは、一万年の間、ずっと絵のスタイルが変わらないことです。
同じようなデザイン、塗り方…まさにイコンのようだと思いました。
描くこと自体が宗教で、描写に制約があるように見える岩絵。
もちろん古代人は発想が貧困で幼稚な絵しか描けなかったんだろう…という事も考えられます。
学ぶべき手本がなければ、こんなモノかもしれません。
でも子供が絵を描く時、目や鼻をちゃんと描くことを考えると、人間を黒く塗りつぶすという行為は表現の一種であり、意図的に人間を影絵のようにデザインしているんだと思いました。
もし古代人が表現力を持っているなら、もっと創造力あふれた絵が本当なら壁を埋め尽くしていると思います。
それがそうじゃなく、型にはまった描写をしていること…そこが気になるのです。
場所が開放的で、絵の内容も牧歌的に見えますが、描き手の心理がそれと同じとは限らないものです。
私はこういう閉鎖された絵を追求するのなら、実際にイコンや仏教絵図を描いているような、個性を最小限度に押さえ、長く同じスタイルを踏襲して描いている職人さんに見てもらい、何を感じるか、共感するものがあるのか…同じ土俵に立つ者としての感想を聞いてみたいと思いました。
一緒に行った先生たちの話ももっと聞いてみたいと思いました。
特に鳴門教育大学の小川先生の感想は色々と聞いてみたかったです。
|